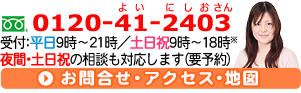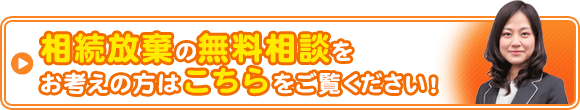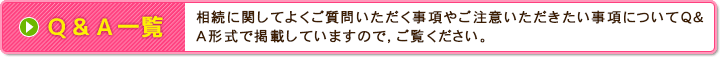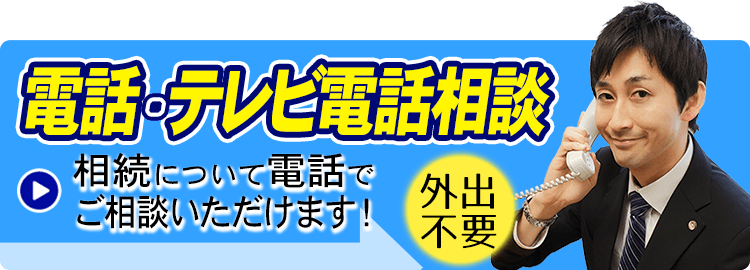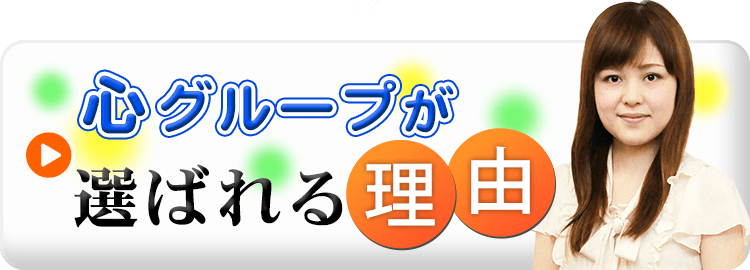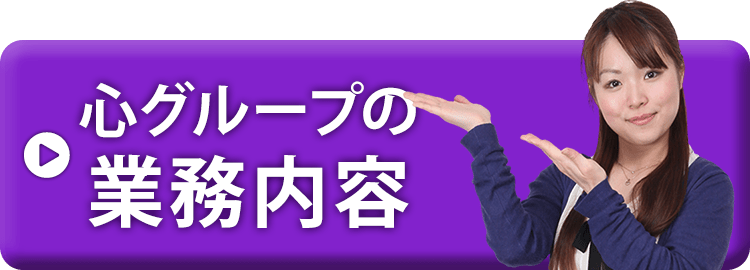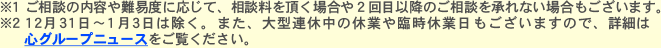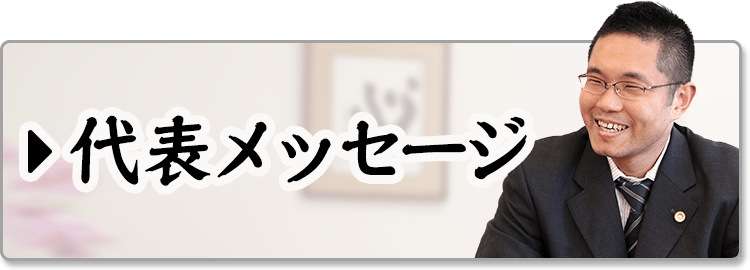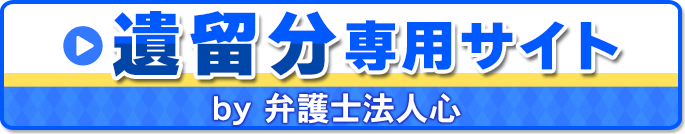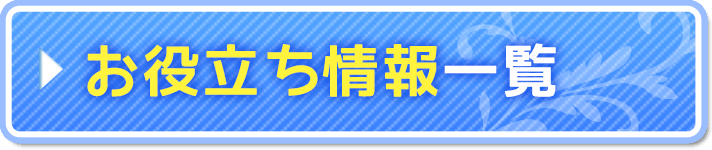相続放棄と相続分の譲渡との違い
1 相続を望まない場合の対応
遺産分割協議においては、相続人全員が合意する必要があります。
遺産分割協議の当事者として、相続人間のトラブルに巻き込まれるのを望まない場合には、「相続放棄」や「相続分の譲渡」といった方法をとることがあります。
いずれも遺産分割協議の当事者でなくなる点では共通します。
しかし、相続放棄と相続分の譲渡には後述のような違いがあるので注意が必要です。
2 手続き・効果の違い
相続放棄は、亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所において申述をする方法で行います。
相続放棄をすると、最初から相続人ではなかったことになるという法的な効果があり、財産も相続債務もいっさい引き継がないことになります。
たとえば法定相続人が子ABCの3人で法定相続分がそれぞれ3分の1ずつであったところ、Aが相続放棄すると、相続人がBC2人のみとなり、BCの法定相続分はそれぞれ2分の1ずつとなります。
これに対し、相続分の譲渡は、相続人が持っていた遺産に対する割合的持分を他の人に移転することです。
先の例で、AがBに対し相続分を全部譲渡すると、Bの相続分は3分の2、Cの相続分は3分の1となります。
なお、相続分を譲渡すると、AとBとのあいだでは相続債務もBが負担することになりますが、Aが債権者から請求を受けた場合には相続債務の移転を主張して拒むことができず、支払義務が残るので注意が必要です。
3 期間の違い
相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月とされており、原則としてこの期間内に家庭裁判所に申述を行わなければなりません。
これに対し、相続分の譲渡は、遺産分割前であればいつでも行うことができます。
4 活用できるケースの違い
相続放棄は、最初から相続人ではなかったことになるだけですが、相続分の譲渡は、譲渡先について、他の相続人でも第三者でも選ぶことができます。
また、有償でも無償でもよく、一部のみを譲渡することもできます。
そのため、自分以外に遺産を相続させたい相手がいる場合や、有償で相続分を現金化したい場合などは、相続分の譲渡に適したケースであるといえます。
また、熟慮期間を過ぎているため相続放棄はできない場合でも、相続分の譲渡を行なえば、遺産分割協議から離脱することが可能となります。
そのため、相続人が多数の事案で長期化しているようなケースでも、状況を整理するために、相続分の譲渡を活用することができます。