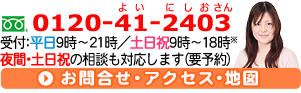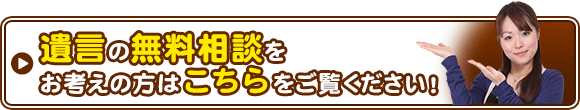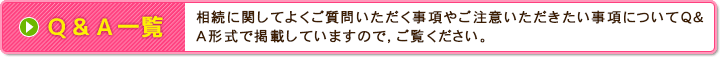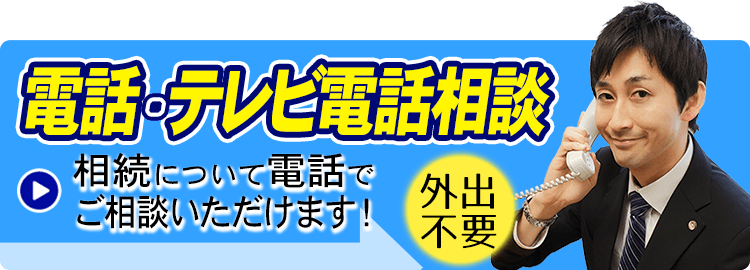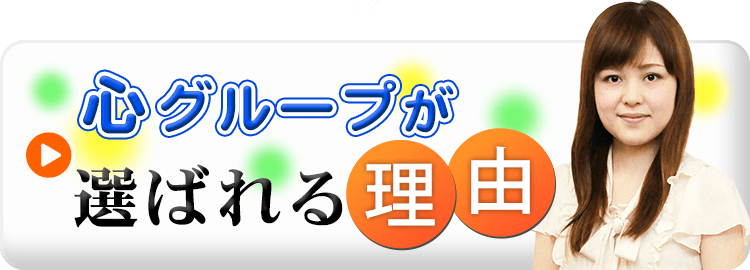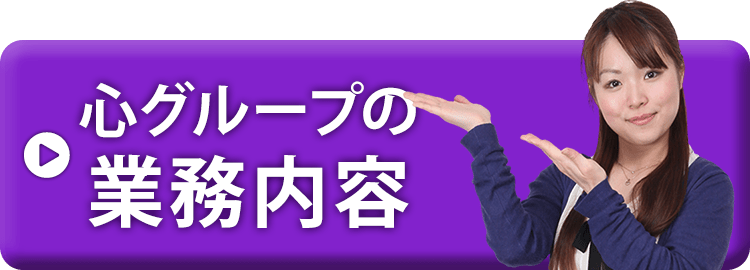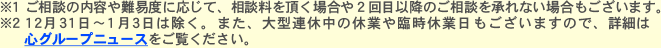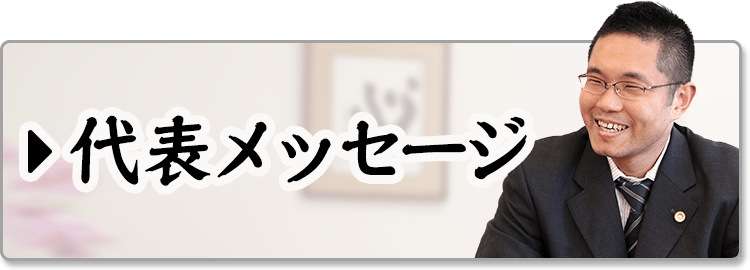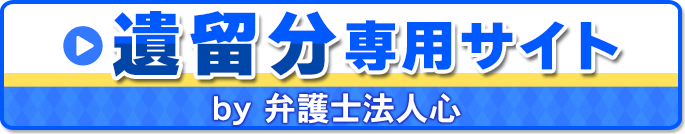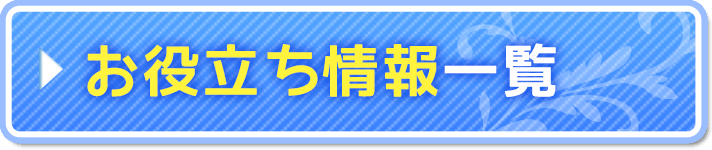遺言の検認手続きの流れと必要書類
1 遺言の検認手続きの流れ
⑴ 検認の申立て
遺言の保管者又は遺言を発見した相続人は、相続開始を知った後に遅滞なく、相続開始地の家庭裁判所に遺言書検認の申立てをしなければなりません(民法1004条1項、家事法別表第1の103項)。
遺言の検認手続きは、原則として、公正証書遺言以外の自筆証書遺言や、その他の方式により作成された遺言書すべてが検認の対象となります。
なお、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用している場合、検認手続きは不要となります。
検認の申立てに必要な書類については、2で説明します。
⑵ 遺言の検認の流れ
まず、相続人等の立会いのもと、遺言書の開封が行われます。
そして、検認期日では、現状を保管するため、家庭裁判所が遺言の方式に関する一切の事実を調査します。
ここでは、遺言書が第三者に改ざんされていないか等を、文字、字体、署名や押印等の外部的状態を確認することにより調査が行われます。
次に、審問が行われます。
審問では、裁判官が、期日に立ち会った申立人ら関係人に対して、遺言がどこで発見されたか、その後どのように保管していたか、被相続人が自分で書いたものであるか、また、本人の印鑑の陰影に間違いがないか等の質問がなされます。
最後に、裁判所書記官が、検認の結果を調書に記載し(家事法211条)、遺言書検認調書を作成することで、検認手続きは完了します。
2 検認の申立てに必要な書類
検認申立書を提出する必要があります。
検認申立書については、書式が裁判所のホームページに掲載されております。
参考リンク:裁判所・遺言書の検認の申立書
また、遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本、相続人全員の戸籍謄本は、提出が必要な書類となります。
遺言者の子(及びその代襲者)で死亡している方がいる場合については、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本も別途提出する必要があります。
以上が全員に共通して提出が必要な書類ですが、その他、相続人が遺言者の父母・祖父母等の場合、相続人が不存在の場合、遺言者の配偶者のみの場合、又は遺言者の兄弟姉妹及びその代襲者の場合等のいずれかにあたる場合は、関係者の戸籍謄本が必要となるため、注意が必要です。
また、場合によっては、当該関係者の出生から死亡までの戸籍謄本を取得する場合もありますので、詳しくは裁判所のホームページをご確認ください。
参考リンク:裁判所・遺言書の検認
ご自身がどの場合にあてはまり、誰の戸籍がどこまで必要なのかを確認することが必要となりますが、戸籍取得には時間も費用もかかるため、困ったら専門家に相談されることをおすすめいたします。
遺言(公正証書遺言)の有無の調査方法 相続が発生した場合の流れと相続手続きのスケジュール